ぐり と グリーンウッドワークでは、事情あって伐られなくてはならなかった木々だけを、原木から手道具で成形して、暮らしの日用品をつくっています。お庭や道路沿い、身近な森で暮らしてきた、多種多様なその木の奥にある聲を聴きながら、感謝を込めて一つひとつデザイン。同じものはありません。フシや樹皮、木目など、その木の生きざまを尊重したデザインには、身近な木々とつながり自然とつながる暮らし――生きものの一員として、あらゆる存在を尊重する暮らし――への願いを込めています。

北欧・英国に伝わる昔ながらの手法で、原木を斧で割って、はつり、ナイフで手削りし、天然の植物油や蜜蝋で仕上げています。

生木(乾燥前の水分を含んだ状態の木)を手道具で削る「グリーンウッドワーク」による日用品づくりの、マンツーマンセッション(orペアセッション)も行っています。
事情あって伐られた身の回りの木をご持参いただいてのセッションも可能です。
木を伐らなくてはならなくなったとき、その木で暮らしの日用品をおつくりすることもしています。(ご依頼はcontactページからどうぞ)

呼ばれるままに
○○をつくりたいから木をもとめる、という順番ではなく、樹種もサイズも多種多様な、そのときどきに出会う木から、呼ばれるままに削っています。
これまでつくってきたものは……

・カトラリ類(各種サイズのスプン、フォーク、バターナイフ、ジャムパドル)+カトラリレスト

・キッチンツール(軽量スプン、コーヒースクープ、菜箸、クッキングスプン、おたま、泡だて器)

・器類(小さな器、豆皿)

・カップ類

・ふた付き容器(スパイスボトル、楊枝入れ、小物入れ)

・インテリア雑貨(削り花フラワーボックス、クリスマスオーナメント、ドアハンガー、小物フック、アロマディフューザー)

・服飾雑貨(ボタン、ブローチ、ポニーフック)

・デスク備品(テープメジャー)

・デスク備品(スマホスタンド)

・文房具(チャーム付きブックマーカー)

・文房具(ペン、えんぴつ)

・アウトドアアイテム(削り屑の着火剤、ポケットスプン、ククサ)

・掃除道具

・家具(子ども椅子、スツール、椅子)
基本、天然の植物油で自然の耐水性を持たせて仕上げています。使うほどに味わいが変化していくのが特徴です。
時折お手入れして、育てながら使っていく「木のもの」たちです。(お直し・お色直しはいつでも送料のみで承ります)。
木々の存在を感じて

庭の木々、街路樹、川べりの木々、近所の森の木々、山歩きするときに出会う木々……。
身近な木々たちは、ずっとそこに立って、日々の暮らしを伴走してくれています。
おいしい空気をつくって、こもれびや新緑、涼しい木陰、花や実、紅葉などで愉しませてくれるだけでなく、ほかの木々や動植物たちとコミュニケーションをとりあって、その場が少しでも、あらゆる生きものにとって過ごしやすい場になるよう調整しています。
気づかぬうちに、さまざまなインスピレーションを私たちの意識の中へと送り込んでくれてもいます。(お釈迦さまは無釉樹の下で生まれ、菩提樹の下で悟りを開きました)。
気づかぬうちに、さまざまなインスピレーションを私たちの意識の中へと送り込んでくれてもいます。(お釈迦さまは無釉樹の下で生まれ、菩提樹の下で悟りを開きました)。
木々と近づいてみよう、と意識を開いたらすぐさま、木々はたくさんのことを開示してくれます。

人間を中心にものごとをみるところから、一歩視点をずらして、ほかの動植物の視点からみてみよう、生態系全体からみてみよう、という脱人間中心主義の動きが、近年、土木や農林業だけでなく科学や行政の領域にも見られるようになってきました。
これをさらに、足元の日常生活にも浸透できたら……
動植物にも、水にも、土にも、地下資源にも、風にも、もっと敬意をもって接するようになったら……
やみくもに「利用」したり「排除」したりするマインドセットから抜け出せたら……
とてもおおきな安心がやってくるんだろうと思います。
どんな姿をした虫にも、生活があり、尊厳がある。
どんな場所に育っている植物にも、生活があり、尊厳がある。
どんな境遇にある動物にも、生活があり、尊厳がある。
形や表現が違えど、尊厳は同じです。
 日本列島は約2/3が森で覆われています。いわゆる”先進国”(OECD加盟国)の中で、フィンランド、スウェーデンに次いで3番目に高い森林率。
日本列島は約2/3が森で覆われています。いわゆる”先進国”(OECD加盟国)の中で、フィンランド、スウェーデンに次いで3番目に高い森林率。太古の時代からずっと、森ではさまざまな生きものが共存してきました。ひともその一員として、森の恵みを受けて暮らしてきた長い歴史があります。
かつて、ひとの活動の高まりによって森がかなり失われて、はげ山ばかりになっていた時期もこの列島にはありました。
いま森林率がここまで回復したとはいえ、いろんな意味で健全とは言えない状態の森が多々あるのも事実です。
今この列島にある森に、木々に、生態系の一員としてどう貢献できるかを、よかったらご一緒に考えていきませんか。
まずは具体的に、暮らしのなかで身近な木々と親しむところから……^_^









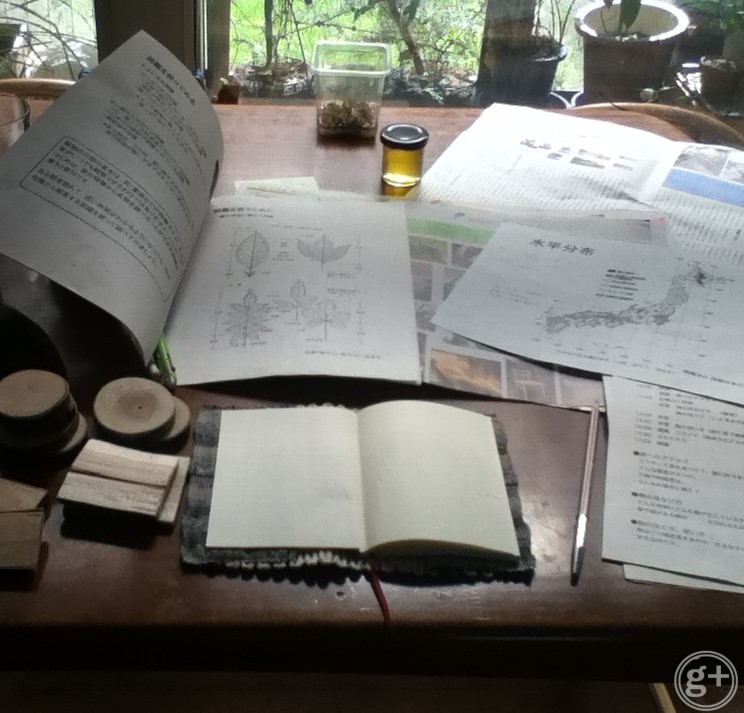


 contact
contact